新宿で開催された、日月潭紅茶のセミナーに参加してきました。
このセミナーは、楽天に出店している台湾の食品やお茶を紹介するセレクトショップ・好時・好食goodtimesgoodeatsさんが主催し、日月潭の紅茶専門メーカーである、和菓森林(HUGOSUM)の総経理・石 茱樺さんが講師を務めるというもの。
生産者の方が日本に来て話をしてくれる機会というのは、あまり無いので、ちょっと急でしたが出かけてきました。
会場は新宿御苑近くの高層マンションの最上階。
キッチン付きのレンタルスペースになっているようでした。
台湾紅茶の歴史と日月潭という土地
はじめに台湾紅茶の歴史についての解説がありました。
日本人の方の通訳付きです。

ポルトガル人が名付けた「麗しき島」という意味のFORMOSA(フォルモサ・美麗島)。
その中部の山間部を「水沙連」と呼んでいたのですが、そこには茶があることが文献で記されていたそうです。
清の時代にも、これらの改良やアッサム種の導入などを行ったようですが、上手く行かず。
日本統治時代になってから、日月潭周辺の魚池で試験生産されたアッサム茶が、ロンドンの品評会で高評価を得たことをきっかけに、魚池での紅茶生産の可能性に期待が高まっていきます。
この地域の風土・気候が大葉種の生育にきわめて適していたためです。
1936年には茶業試験場の魚池分場が設置され、その後、タイからシャン種、ビルマからバーマ種が導入されるなどして、大葉種を用いた紅茶の産地として、産業化が図られていきます。
ここに大きく携わったのが、台湾紅茶の父として知られる、群馬県出身の新井耕吉郎氏。
日本人経営による茶園も増えていき、その中でも最も広い栽培面積を誇っていたのが、持木壮造氏による持木興業合資会社。
1932年に創業し、往時は年間2万7千斤もの生産を行っていたそうです。
終戦後、この工場は中華民国政府に引き継がれ、生産を続けることになります。
ここに勤務していたのが、講師の先生の父上である石 朝幸氏。
終戦後も台湾の茶業伝習所に残っていた日本人の下で、製茶技術を学び、故郷に近い、この工場に派遣されたそうです。
そして、工場主任を務めたあとに退職し、紅茶の生産を自分で始めたのだとか。
このように、台湾紅茶の歴史は、日本がかなり深く関わっているので、面白いですね(^^)
和菓森林ブランド
2代目である、講師の石 茱樺さんは、元々は別の会社に勤務していたそうですが、10年ほど前に家業を継ぐために戻ってきたとのこと。
長らく、魚地の主要な産業であった紅茶ですが、海外とのコスト競争力の問題に加え、1999年に発生した921大地震で大きな被害を被ったことから、徐々に衰退しつつありました。
「私が戻らなければ、なくなってしまう」ということで、戻ってきて以来、伝統的な製法はそのままに、新しい取り組みをいろいろと行っています。
その中心にあるのが、自社ブランドである「和菓森林」というブランドです。
まず、除草剤や農薬を用いない、自然栽培を行っていること。
肥料も有機肥料を使用しているとのことで、安心・安全を守って生産をしているそうです。
さらには、日月潭紅茶の原産地認証も取得しているそうです。
新しい試みとしては、ヴィンテージ紅茶を発売したり、製茶体験、茶葉料理の提供など、観光と組み合わせた新しい茶業にも挑戦しているとのことです。
生産者の方といっても、誰でも理路整然とお話しできるわけではありません。
今回のセミナーはかなりしっかりした作りになっていたのですが、それは日頃からレクチャーすることに慣れていらっしゃるからですね。
3種類のお茶を試飲
同社では、大葉種の紅茶のみを生産していますが、品種の違いでお茶がラインナップされています。
今回はその中から3種類、祖母緑紅茶(日本時代からの老叢。80年ぐらいのもの)、紅玉紅茶(台茶18号)、紅宝石紅茶(自生していた山茶)を鑑定杯形式で試飲しました。

独自のテイスティングシートを用いながら、お茶の印象を記していきます。
老叢で作った祖母緑紅茶は、柔らかい口当たりながら余韻は長め。渋みも少なくストレートでいただきたいお茶です。
紅玉紅茶は、独特のメンソール感がよく出ていましたが、渋みや雑味が少なく、丁寧な製茶をしていることが感じ取れました。
山茶で作った紅宝石紅茶は、意外にパンチのある味わい。香りもハッキリしていましたが、余韻の長さが印象的です。
どのお茶も、水色は比較的淡めで南洋の紅茶に比べると香りや味わいは穏やかです。
が、丁寧な仕事で作った紅茶だという感じがします。
烏龍茶好きの方が切り替えても違和感のない飲み方ができそうな紅茶です。
スイーツとのペアリングも
2煎目は、同じお茶をお菓子と合わせたときにどうなるか?を実験しました。
用意されたお菓子は、水ようかん、チーズケーキ、パイナップルケーキの3種。

これらが、それぞれのお茶に上手く合うというので、その実験をしました。
お茶によって、塩味があった方が良いとか、フルーツに合うとか、いろいろ違いがあるのです。

さらにこの日の東京は気温が35℃の予報ということで、紅玉の冷茶もワイングラスに入って登場。

水出しですが、しっかりメンソール感は出ていて、飲んだ瞬間「あ、紅玉」と分かるお茶でした。
夏にメンソール感は、スッキリするので、良いですね(^^)
急須でアッサムと台茶8号も
最後に急須を使って、アッサム種の紅茶と台茶8号も淹れていただきました。
工夫茶の実演ということなのですが、多くの茶器・茶道具があると、慣れない人は却って難しく感じてしまうということで、必要最小限の器具での実演となりました。
 鑑定杯で淹れるのとは、やはり香りの立ち方が違いますね。
鑑定杯で淹れるのとは、やはり香りの立ち方が違いますね。
同じ日月潭の紅茶といっても、やはり品種によって、だいぶ味は違うなぁ、とよく分かるものでした。
と、かなり中身の充実した140分間のセミナーでした。
終了後、今回は急なことで参加できなかった方もいますし、生産者の話は聞きたい方がたくさんいます、と主催者の方にお伝えしておきました。
今度やるときは、もう少し早めに教えてもらえるとのことなので、気になる方は、中国茶情報局を定期的にチェックしてみてください。
なお、和菓森林さんの製品は、台北には代理店が無いので、現地でも魚池まで行かないと買えないそうです。
楽天に出店している好時・好食goodtimesgoodeatsさんは、日本の正規代理店とのことなので、お茶を試してみたい方は、ぜひそちらで。
![]()
台湾紅茶も面白いですよ(^^)







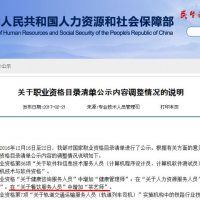



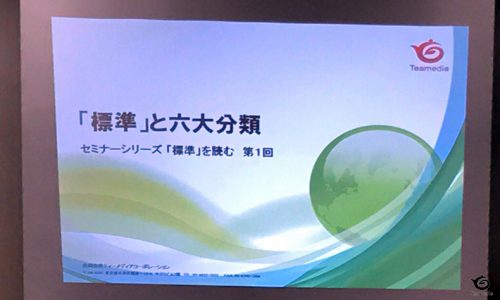



この記事へのコメントはありません。